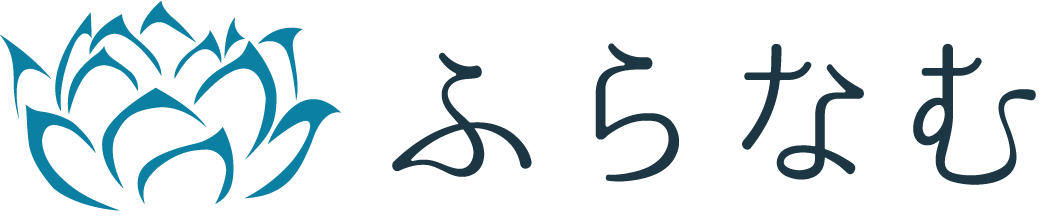仏花(ぶっか)とは、簡単にいうと「仏壇やお墓にお供えする花」です。
仏壇にお供えする花を「仏花」、お墓にお供えするものを「墓花」と区別することもありますが、どちらも仏花と言うこともあります。
最近では、花の種類や供え方の厳密な決まりはなくなってきていますが、いざという時のために最低限のマナーを知っておくと安心です。
ここでは、仏花の由来やマナーについて、わかりやすくまとめてご紹介します。

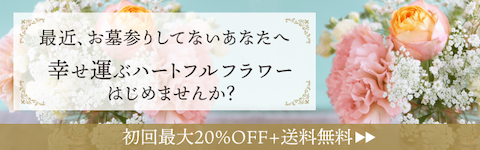
仏花は何のために供えるの?
仏壇やお墓にお花を供えることは昔から当たり前のように行われています。
でも、あらためて何のためかと聞かれたら答えるのはむずかしいですよね。
仏花を供える理由は、大きく分けると2つあります。
仏教的な意味合い

お釈迦さまが悟りを開く前に修行していた時代のこと、燃灯仏(ねんとうぶつ)という仏様が現れて、「後に仏になる」という予言を授けたのだそうです。
お釈迦さまは、燃灯仏に何かお供えをしたいと思いましたが、周囲には何もありませんでした。
そこで、近くにいた花売りの少女から青蓮華(しょうれんげ)という花を買って供えたのだそうです。
このお話が、仏花の始まりと言い伝えられています。
仏教では、お釈迦さまの逸話のようにお花を供えることが仏様を敬い、修行する誓いを立てることにつながると考えられています。
また、「花」は、厳しい状況でも生き抜くことから、お手本にする存在としてもとらえられています。
亡くなった方への想いを表すため
2つ目は、私たちにとってもわかりやすい理由です。
亡くなった方を想い、その方の好きだったお花を選び手を合わせることで、会話をしているような気持ちになれるのです。
仏花を供えることで、静かに亡くなった方に想いをはせることができ、悲しみを乗り越えることにもつながっていきます。
仏花は、亡くなった方のためだけでなく、供える人の心も優しく包んでくれます。
仏花に造花を使ってもいい?
「仏様に造花を供えてはいけない」とか「仏様には生花」と聞いたことがある方もいるかもしれません。
今では、生花と変わらないようなプリザーブドフラワーも出てきていて、造花はよくないという考え方も薄れつつあるようです。
忙しくて毎日の水換えが大変なときには、上手にプリザーブドフラワーを取り入れるのも賢い方法と言えるでしょう。
ただ、こうした時代の流れがあっても、お盆やお彼岸、法要など亡くなった方をお迎えするような場合の仏花には、今も必ず生花が選ばれています。
「仏花には生花の方がふさわしい」という考え方は単なる昔からの習慣ではなく、それなりの意味があるのです。
仏花には生花がふさわしい理由
仏教には「諸行無常」という考え方があります。すべてのものは移り変わり、変わらないものはないと言う意味です。
作りものではない生花は、たとえ毎日お水を換えたとしてもいずれは枯れてしまいます。
その枯れてゆく姿から、私たち人間の命が今日あることも、当たり前ではないことだと再確認ができるのです。
また、ご先祖様は食べ物の代わりに花の香りを楽しんでいらっしゃると考えられていることからも、生花の方がふさわしいと言われています。
生花の水換えや新しい花を準備するひとときに、亡くなった方を想い、静かに向き合うことができるということですね。
仏花の生け方と注意点

最近では、厳密なルールはなくなってきていますが、いざという時のために覚えておきたい仏花のマナーをご紹介します。
仏花の生け方
<左右に一対が基本的な生け方>
仏花は「一対でないとダメ」と聞いたことはありませんか?
仏教では左右対称のものを円の代わりとして「輪廻」を表現します。
そのため仏花も同じお花を左右に供えるのが基本的な生け方です。
<お花の数は奇数にする>
お花の数にも決まりがあり、花の数は奇数にするのがよいとされています。
例えば、花束を2つ供える場合は、1つの花束の花の数が奇数になるようにします。
これは、古来から、割ることのできない奇数の数の方が縁起がよく、力が宿るとされているからです。
仏事に縁起がよい奇数を使うのは不思議な気もしますが、亡くなった方が来世でも幸せであることを願う気持ちの表れかもしれません。
仏花には向かない花
<トゲのある花>
トゲのある花を供えても問題はありませんが、お供えするときに、ご自身が怪我をしたり 他の参拝者の方、墓地や霊園管理者が花の片付けをするときにもケガをしないように配慮が必要です。
亡くなった方が好きだった場合には、バラを選ぶことも増えてきています。
・トゲのある花の例…バラ・アザミ・.サボテン
<香りの強い花>
部屋中に香りが広がるような花は、お線香の香りと混ざってしまうことから、避けるのがマナーです。
しかし、仏様は香りを楽しむという考え方もあることから、お線香を焚かないときにあえて香りの強い花を仏花とすることもあるようです。
・香りの強い花の例…カサブランカ(ユリの一種)
<毒のある花>
毒が含まれるお花は、仏様に毒をお供えすることにつながってしまうので、避けた方がよいとされます。
人気の高いチューリップも球根に毒性があるため、本来は仏花には適していません。
ただし、亡くなった方が好きだった場合は、あえてチューリップをお供えするケースもあるようです。
・毒のある花の例…水仙・彼岸花・チューリップ
<ドライフラワー>
ナチュラルなインテリアにはぴったりのドライフラワーですが、メインの仏花にするのは避けておいた方がいいでしょう。
ドライフラワーは花を乾燥させて作るので、枯れるというイメージがあり、縁起が良くない点や香りがしないことが向いていないとされています。
仏花の色選び
仏花の色には、かつてはルールがありました。簡単に紹介すると、下記の通りです。
【四十九日まで】
白一色か「白・黄・紫」の3色
【四十九日を過ぎてから】
「白・黄・紫・ピンク・赤」の5色
この決まりは仏教に由来したものです。
仏教では、人が亡くなると、四十九日間をかけてあの世への旅をすると考えられています。
旅の途中では、供えられた花の色を通して現世が見えるのだそうです。
そのため振り返ることなく、成仏してもらうために、四十九日までは、花の色味を抑える風習があったのです。
そして、四十九日の法要のあと、仏様は祭壇(現世)から仏壇(極楽浄土)へと移られると考えられています。
「白・黄・紫・ピンク・赤」の5色は、仏教でよく使われる色で仏教の寺院を表し、仏花の場合には、5色の花が仏さまの体の代わりになるとも言われています。
仏教では、仏さまはお供えした花の姿で、私たちを見守ってくださっているとされているのです。
マナーを知って自由に選ぼう
今では、仏花の色選びに厳密なルールはなくなり、「四十九日までは色を抑えめにする」というぐらいの感覚になっているようです。
法要のための仏花は、地域や宗派によってしきたりがある場合もありますので、確認してみましょう。
仏花のマナーをふまえながらも、亡くなった方の好みや雰囲気に合わせたお花を選んでみると、特別なお花をお供えすることができそうですね。
親しい人だけで集まるお盆やお彼岸には、自由に新しいタイプの仏花を取り入れてみてはいかがでしょうか。

おわりに
ここまで仏花の由来やマナーについて解説してきました。
まとめとして最後に主なポイントを振り返ってみましょう。
【仏花は何のために供えるの?】
- 仏教では、お花を供えることが仏様を敬い修行する誓いを立てることにつながると考えられている
- 亡くなった方へ想いを表すことができるとともに、供える人の心も優しく包んでくれる
- ご先祖様は食べ物の代わりに花の香りを楽しんでいらっしゃると考えられている
【仏花の生け方と注意点】
- 左右に一対同じ花を供えるのが基本的な生け方
- お花の数は奇数にする
- 香りの強い花、毒のある花、ドライフラワーは仏花に向いていないとされている
- 四十九日までは仏花の色を抑えめにする
ご紹介したマナーは、最近では必ずしも守らなければならないものではなくなってきています。
それでも、弔問客を迎える立場になったときやお世話になった方に仏花をお贈りするときのために、知っておくと安心できるでしょう。
マナーを知ったうえで、亡くなった方を想う気持ちを大切に仏花を選んでみてはいかがでしょうか。
お花をお供えする際には、仏壇や花瓶がなくても簡単に飾ることができる、ふらなむの「ハートフルフラワー」がおすすめです。